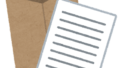ご覧いただきありがとうございます。
退職してはや3ヶ月。セミリタイア生活も慣れたものになりました。
先日取得した簿記2級にはじまり、すっかり勉強が習慣になってきました。
近頃は、会計や法律だけでなく、ひさしぶりに文学や歴史など、教養科目についても手が伸びるようになってきています。
今回は、セミリタイア生活と学問について、思ったことなどをまとめていきます。
教養科目を勉強しだした経緯
退職後の生活リズムにも慣れ、毎日のルーティンも確立してきました。生活の大部分を占めてきた勤労時間もなくなり、家事や子供との時間以外は、自分の時間が増大しています。
私はセミリタイア生活での収入の1つとして、士業資格での個人事業を目論んでおり、その取得に向けての勉強に、結構な時間を当てておりました。そんなおり、どうも試験日や模試の成績が気になり、隙間時間を見つけては勉強をするようになって来ていました。
勉強習慣がついた事自体は良いのですが、役に立つこと・お金に変わること、ばかりを追い求めると、仕事をしていた時のように効率や成果に追われて、心が休まらない現状に気づきました。効率的に勉強をするのも良いのですが、関係する専門書も参照しながら、のんびり進めて、知識に深みをつけたいと思いました。
加えて、幸運なことにせっかく多くの時間を得たのだから、『すぐには役に立たない、お金にならない』ような学問も、知的好奇心のままにやってみようと思ったのが、始めた経緯です。学ぶこと自体が楽しい、その感覚が久しぶりに蘇りました。
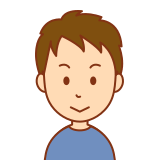
「すぐに役立つもの」ばかり、追い求めるのも疲れました
文学・哲学について
そんな思いつきも、すぐに取り組めるのがセミリタイア生活のメリットです。久しぶりに文学作品を読み返したり、どこかの大学の聴講生になるのも考えたりしています。文学は結構好きだったので、若い頃は、和洋問わず結構な乱読をしていました。
また、学生時代には食指が動かなかった、哲学にも興味が出てきました。文学とは違い、哲学書はあまり読んだことがなかったので、どこから始めようかと思っていたところ、良さげな本を見つけたのでご紹介。
この本によると、フランス人は高校生で哲学が必修科目として課されるそうです。哲学の思想や手法を学び、一定の型を使って、問いをたて、論述していく方法が紹介されていました。哲学という難解な学問の試験でも、一定の方法論によって回答できることを初めて知りました。フランスの学校で学ぶ哲学者や、参考書籍も紹介されていたので、とっかかりにしてみようと思います。
ふと思ったのですが、哲学とセミリタイア者は、結構親和性があるような気がします(笑)。哲学だけで生計を立てようと思うと、相当な困難がありそうです。昔の哲学者も裕福だったり、パトロンがいたりで、生活するに不自由がなかったからこそ、あれだけ思索することができたのでしょうか。
まとめ
古代の哲学者や、文学が好きな高等遊民など、経済的価値に繋がりにくい学問や芸術は、自由な時間がないとできないのだなと思ったりします。
例えば、何かやりたいこと(芸術や学問)がある人は、以下の戦略を取ることも検討に値します。
①まずは就職しセミリタイアを目指す。
②セミリタイア後は、最低限の労働と資産収入で生計を維持しつつ、自分の目標に使う時間を増やしていく。
③その後やりたいことで、生計が立つようになれば、万々歳。
④仮に希望の分野で生計は維持できなくとも、フルタイム勤務の必要はないので、引き続き興味関心に時間を使える。
私のような凡人は、最初から自分の夢にフルコミットは、怖くてとてもできそうにありません(笑)。定年後の第二の人生で始めるよりは、ちょうど折り返し地点で、自分の夢に着手開始できます。若い頃に、こういった考えを知っていたら、あそこまで絶望的な気持ちで就職していなかったかもと思ったります。